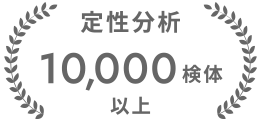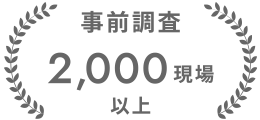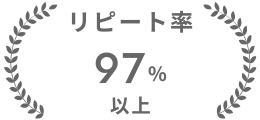太陽光パネルの大量廃棄に備えてリサイクル技術の確立が急務
太陽光パネルは寿命が25〜30年とされ、2030年代には年間17万〜28万トンもの「大量廃棄時代」が到来すると予測されています。この膨大な量のパネルを適切に処理できないと、最終処分場の逼迫や不法投棄による深刻な社会問題を引き起こす可能性があります。
太陽光発電が抱える廃棄物問題を解決し、持続可能性を確立するためには、埋め立て処分ではなく、資源を回収・再利用する高効率なリサイクル技術の確立と普及が不可欠です。
今回の記事では、太陽光パネルのリサイクルがなぜ難しいのか、その基本的なプロセス、現在注目されている具体的なリサイクル技術について徹底解説します。
太陽光パネルの廃棄・リサイクルの現状

現在、使用済み太陽光パネルの多くは産業廃棄物として最終処分場に埋め立てられています。しかし、前述の通り、2030年代の大量廃棄が現実となれば、既存の最終処分場だけでは対応しきれない事態が予想されます。
環境省が公表している「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」では、使用済み太陽光パネルの処理に関して、排出事業者に以下の優先順位を推奨しています。
①リユース(再利用):発電能力が残っているパネルを再販・再利用する。
②リサイクル(再資源化):パネルを分解し、素材ごとに資源として回収・再利用する。
③埋立処分(最終処分):上記が困難な場合に、適正な方法で埋め立てる。
このガイドラインが示すように、環境負荷を低減し、持続可能な社会を築くためには、リサイクルやリユースの推進が最優先課題です。
しかし、現状ではリサイクル技術の実用化や普及には多くの課題が残されており、費用面でも埋め立て処分の方が安価なケースが多く、リサイクルへの移行は十分に進んでいません。
国は2022年7月に「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度」を導入し、廃棄費用の確保を義務化しましたが、これは廃棄物の適正処理を促すものであり、リサイクルを直接義務付けるものではありません。いかにリサイクルの割合を高めていくかが、喫緊の課題となっています。
※参考サイト:太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン https://www.env.go.jp/content/000245687.pdf
太陽光パネルのリサイクルが進まない5つの理由

太陽光パネルのリサイクルが進まない背景には、主に5つの大きな理由が挙げられます。これらの課題を解決することが、リサイクル推進の鍵となります。
技術的課題1:複合素材の分離困難性
太陽光パネルは、長期の屋外使用に耐え、発電効率を維持するために非常に強固な構造をしています。ガラス、EVA樹脂(封止材)、セル(シリコンなど)、裏面シート、アルミフレームといった複数の素材が何層にもわたって強力に接着されているため、これらを効率的かつ低コストで分離・分解する技術の確立が最大の課題です。
手作業での解体はコストがかかりすぎ、また単純な破砕では素材が混ざり合ってしまい、高純度の資源回収が困難になります。
技術的課題2:有害物質の適正処理
一部の太陽光パネルには、鉛、カドミウム、ヒ素、セレンなどの有害物質が含まれている場合があります。これらの物質が適切に分離・処理されないまま埋め立てられたり、不法投棄されたりすると、土壌や水質汚染の原因となる深刻な環境リスクが生じます。
有害物質の情報が処理業者に正確に伝わらない場合、適切な処理が行われない懸念もあり、JPEA(太陽光発電協会)がガイドラインを策定するなど、情報共有の仕組み作りも進められています。
経済的課題3:リサイクルコストの高さ
現状の技術では、太陽光パネルのリサイクルにかかるコストが、単純な埋め立て処分にかかる費用よりも高くなる傾向があります。
これは、複合素材の分離にかかる手間や、専用のリサイクル設備の導入・運用に多額の費用がかかることなどが原因です。経済的なインセンティブが十分に働かないため、事業者はより安価な埋め立て処分を選択しがちです。
経済的課題4:回収資源の市場価値の低さ
太陽光パネルから回収される素材(特にガラスなど)の市場価値が低いことも、リサイクルの普及を阻む経済的な課題です。
リサイクルを本格的に普及させるには、より低コストで高リサイクル率を実現できる技術の開発と、回収資源の市場価値を高める用途開拓、そしてリサイクルを支援する経済的な枠組み(補助金や助成金制度)の充実が不可欠です。
制度的課題5:リサイクル制度の未整備と情報の散逸
EU諸国では「WEEE指令」で使用済み太陽光パネルの回収・リサイクルが法的に義務付けられ、メーカーにリサイクル費用負担を義務付ける拡大生産者責任(EPR)の考え方が導入されています。しかし日本では、太陽光パネルのリサイクルに関する明確な法的義務付けや制度がまだ十分に整っていません。
リサイクルやリユースに関するルールが未整備であるため、使用済みパネルの発生量や処理・リサイクルの実態に関する情報が一元化されておらず、全体像の把握が困難な状況です。
最先端!太陽光パネルのリサイクル技術4選

効率的かつ低コストなリサイクルを実現するため、様々な分離・回収技術が開発され、実用化が進んでいます。これらの技術は、回収される素材の純度や処理効率、コスト面でそれぞれ異なる特徴を持ちます。
※参考サイト:太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン https://www.env.go.jp/content/000245687.pdf
技術1:二軸破砕機による分別
二軸破砕機は、二つの回転するロールでパネルを挟み込み、物理的に破砕・分離する装置です。まずアルミフレームを取り外した後、ガラスとセル、封止材(EVA)の複合体を破砕機に通し、ガラスを細かく粉砕することで、他の素材との分離を容易にします。
アルミ枠分離装置とガラス分離装置が一体型となったシステムもあり、工程効率化が図れます。大量のパネル処理に適し、初期段階での一次破砕や粗分離に用いられ、破砕されたガラスは路盤材やセメント原料などに再利用されます。
技術2:ホットナイフによる分別
高温に加熱された特殊な刃(ホットナイフ)を使用し、太陽光パネルのガラス層とEVA樹脂層の接着部分を溶かし分離する技術です。刃を層間に挿入し熱で接着剤を軟化させることで、ガラスを破がします。
この方法の最大の利点は、ガラスを破砕せずにそのままの板状で回収できるため、建築用板ガラスやガラス繊維など、より高付加価値な用途での再利用が期待できる点です。ただし、パネルの製造方法や劣化、変形状況によっては分離が困難なケースもあります。
技術3:ブラスト工法による分別
粒状の投射材料(ショットメディア)を圧縮空気などでパネル表面に高速で噴きつけ、その衝撃力でガラス層やEVA樹脂を物理的に剥離させる技術です。
アルミフレームを取り外した後にこのプロセスを行うのが一般的です。非接触に近い形で分離を行うため、パネルのシート面やセルへのダメージを最小限に抑えつつ、ガラスやEVAを剥がします。回収される素材の純度を高められるので、特にガラスのリサイクル率向上に効果的です。
技術4:回転ハンマー打撃工法による分別
加熱処理を施した太陽光パネルに対し、高速回転するハンマーで物理的な打撃を加え、ガラス、EVA樹脂、セルといった各層を剥離させる技術です。従来のガラスの剥離性の弱さを補うことを目的として開発されました。
パネルの割れや変形に左右されずに処理が可能であり、幅広い状態のパネルに対応できます。付着物をほぼ完全に取り除き、回収されるシートやセルの純度を大幅に高められるため、高品位な再資源化が期待されます。
太陽光パネルのリサイクルはオルビー環境へ

太陽光発電設備の大量廃棄時代が目前に迫る中で、リサイクル技術の確立と普及は、持続可能な社会を実現するための喫緊の課題です。
国は「廃棄等費用積立制度」を導入し、廃棄費用の確保を義務付けましたが、真の解決には、いかに効率的かつ環境負荷の低いリサイクルを推進するかが鍵となります。
オルビー環境では、関西エリア(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)を中心に全国対応で、太陽光パネルのリユース・リサイクルに関するソリューションを提供しています。太陽光パネルの廃棄に関してお悩みでしたら、ぜひオルビー環境へお気軽にお問い合わせください。